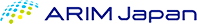共用装置
【オンライン+現地開催】物質・材料研究機構:R7年度第二回 マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)NIMS担当領域セミナー「ARIM利用で加速する研究・開発 -電子顕微鏡編-」(2025年7月29日)を開催いたします
本セミナーでは、NIMS-ARIMで利用できる電子顕微鏡等の概要とその応用例についてご説明いたします。さらに、実際に電子顕微鏡を利用しているNIMS研究者から、具体的な研究事例や成果についてご紹介いたします。
セミナー終了後には、人数限定で電子顕微鏡等の見学会と個別相談会を実施します。実際の装置を間近でご覧いただき、また日頃の疑問を専門家に直接質問できる貴重な機会です。
※参加人数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。
日時
2025年7月29日(火)13:30-15:30
開催方式
オンライン併用
場所:物質・材料研究機構 千現地区第2会議室
主催
マテリアル先端リサーチインフラ NIMS担当領域 量子・電子マテリアル領域/マテリアルの高度循環技術領域
共催
技術開発・共用部門 材料創製・評価プラットフォーム 電子顕微鏡ユニット
定員
会場 50名
参加費
無料
参加申し込み
Webフォーム https://nims-arim.webex.com/weblink/register/r54e095eab43ccb54e0be844912f538b3
申込締切:7月25日(金)
詳細
【プログラム】
第1部 13:30-15:00 NIMS-ARIM担当領域セミナー(ハイブリッド)
第2部 15:00-15:30 特別企画(オンサイトのみ)
I:装置見学会(電子顕微鏡及び試料作製装置、他)
II:電子顕微鏡ユニットスタッフによる個別技術相談会
2025年度 第1回ARIM量子・電子マテリアル領域セミナーを開催いたします
物質・材料研究機構、東京科学大学、北海道大学、産業技術総合研究所は、令和3年度からスタートした文部科学省委託事業である「マテリアル先端リサーチインフラ事業(ARIM)」の一環として、『施設共用におけるALD成膜のユーザー事例紹介』というオンラインセミナーを2025年8月6日(水)にTeams配信により開催いたします。ARIM共用事業では、これまでの施設利用に加えて利用結果のデータベース化とそれらのデータの利活用が大きな事業目標となっています。
今回は、これまでの様々なALD成膜事例についてユーザー様からご紹介いただきます。また、データベースの閲覧環境が整いつつありますので、その閲覧方法やデータカタログの一部を紹介いたします。詳細はこちらからご確認ください。
講演
【日時】 令和7年8月6日(水)12:55~17:00
【Teamsによるオンライン配信】 URLは、開催日までに連絡します
【定員】 200名(先着順、参加登録をお願いします)
【参加申込】 https://www.tia-kyoyo.jp/npf/seminar/2025-1/book/
【参加費】 無料
【お問い合わせ】 tia-npf-school1@aist.go.jp
主催・共催
【主催】 産業技術総合研究所ナノプロセシング施設運営室(NPF)
【主催】 物質・材料研究機構 ARIMセンターハブ担当領域推進室
【主催】 東京科学大学ナノ構造造形支援事業
【主催】 北海道大学総合イノベーション創発機構ナノテクノロジー連携研究推進室
お問い合わせ
e-mail:tia-npf-school1@aist.go.jp
令和7年度第1回合成横断技術領域ワークショップを開催いたします
先端分析技術である「局所分光法」──原子間力顕微鏡(AFM)と分光を融合したこの技術は、今まさに材料科学・生命科学・半導体分野に革新をもたらしつつあります。本ワークショップでは、ナノスケールでの分光技術に関する最新の研究成果と開発動向を、トップ研究者と最前線の企業技術者よりご紹介いただきます。Nano-IRやTERS(探針増強ラマン分光)に関心をお持ちの方、あるいは今後の研究・装置開発にヒントを得たい方など、どなたでもご参加いただけます。詳細はこちらから
開催概要
•日時:令和7年7月17日(木)13:30~18:30
•会場:電気通信大学(対面・オンラインのハイブリッド開催)
•参加対象:制限なし(どなたでもご参加いただけます)
•参加申し込み:https://forms.gle/J1DzwEvcXBAiX98FA
•定員:現地参加60名、オンライン参加:制限なし
プログラム(敬称略)
13:30~13:35 開会挨拶
河合壯(ARIM合成横断領域代表、奈良先端科学技術大学院大学教授)
13:35~14:25 「探針増強近接場分光の最前線:単一原子・単一分子・ナノマテリアルの精密分光」
熊谷崇(分子科学研究所准教授)
14:25~15:10 「ナノの世界を化学する:ナノ分解能の新しい赤外分光技術Photothermal AFM-IR」
横川雅俊(ブルカー・ジャパン株式会社ナノ表面計測事業部)
15:10~15:20 休憩
15:20~16:10 「ナノカーボン材料のAFM-TERS評価」
吉村雅満(豊田工業大学教授)
16:10~16:25 「電通大におけるARIM装置の紹介」
平野誉(電気通信大学教授)
閉会後のプログラム(希望者のみ)
16:30~17:15 電気通信大学施設見学
17:30~18:30 情報交換会(対面)
技術の“今”を体感し、第一線の研究者と直接交流できる貴重な機会です。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
≪終了いたしました≫第9回 北海道大学 微小部・表面分析研究ユーザーズミーティングを開催いたします
工学研究院の共同利用施設では、表面・微小領域分析装置の一般開放を行っております。装置はいずれも試料評価への強力なツールとなりますが、実際に使用する際には各装置の分析法の特徴を理解し、適切な選択を行うことが非常に重要となります。観察・分析技術の向上を目指し、ユーザーの皆様と施設職員の間で「材料分析に関するテクニカルな情報の共有化」を目的として、本ユーザーズミーティングを開催致します。詳細はこちら
会場
フロンティア応用科学研究棟2階セミナー室
日時
2025年5月22日(木)10:30 ~ 17:00
参加費
無料
参加方法
事前の申し込みは不要。オンライン(ZOOM)でも参加可能。ハイブリッド形式での開催です。
セミナー内容
<ユーザーズ講演>
10:35~10:50 「CO2メタネーション用Ni触媒にAg2CO3を混合した際の効果と表面状態の変化」
北海道大学大学院工学研究院修士1年竹内航平
10:50~11:05 「EBSD法によるTi3SiC2の結晶配向評価と変形挙動解析」
北海道大学大学院工学研究院博士1年清英一
<テクニカル講演1>
11:05~12:00 「ナノマテリアルにおける電子顕微鏡前処理技術の進化-最新断面加工装置による観察事例の紹介-」
メイワフォーシス株式会社古瀬光明氏
昼休憩(12:00~13:00)
<ユーザーズ招待講演>
13:00~13:40 「ARIM微細加工/分析装置によって加速する核融合材料・光学材料研究」
自然科学研究機構核融合科学研究所・准教授上原日和先生
<テクニカル講演2>
13:40~14:25 「EPMA-SXES(軟X線発光分光器)の御紹介-基本原理と活用事例-」
日本電子株式会社高倉優氏
休憩(15分間)
14:40~15:15 「EDSの基礎と定量分析のコツ」(オンライン)
日本電子株式会社溜池あかね氏
15:15~16:10 「TEMの原理からJEM-ARM200F NEOARMの特長まで」(オンライン)
日本電子株式会社遠藤徳明氏
休憩(15分間)
16:25~17:00 「オージェ電子分光法の基礎とアプリケーション」
日本電子株式会社鍋島冬樹氏
主催
北海道大学工学研究院共同利用施設複合量子ビーム超高圧顕微解析研究室、
光電子分光分析研究室、ナノ・マイクロマテリアル分析研究室
共催
文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)量子・電子制御により革新的な機能を発現するマテリアル重要技術領域
北海道大学、計測横断技術領域
協賛
日本金属学会北海道支部、日本鉄鋼協会北海道支部、日本分析化学会北海道支部、
日本顕微鏡学会北海道支部、日本電子株式会社、メイワフォーシス株式会社、XPSコミュニティー
令和7年度試行的利用制度受付開始のお知らせ
文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)では、我が国のマテリアル革新力の一層の強化を目的に、最先端設備の共用、高度専門技術者による技術支援に加え、設備利用に伴って創出されるマテリアルデータの利活用の促進を行っております。本制度では、イノベーション創出のための新しい芽の発掘や独創的な研究開発に取り組んでおられる研究者や研究グループに共用設備をご利用いただき、我が国のマテリアル革新力の一層の強化を図るために、共用設備の利用の補助(利用料金と支援機関への旅費の一部)を行います。また、支援機関におかれましては、新規の共用設備の利用者の拡大に、ご活用ください。
お問い合わせはmaterial-dx(at)cris.hokudai.ac.jpへご連絡をお願いいたします。
※(at)を@(半角)に変えて下さい
申請条件(ご利用には審査があります)
以下の条件を満たす研究者であること
利用する支援機関以外の研究機関等に所属する利用課題の代表者(筆頭研究者)で、これまでARIM事業による共用設備の利用経験がなく、申請される利用課題により、今後もARIM事業の利用につながる可能性があると見込める以下研究者。
A)大学・研究開発法人など公的研究機関において、運営費交付金や科研費などの研究費を自身の権限で管理・執行する研究者。ただし、次のいずれかに該当する申請の場合は、原則認められません。
①研究費を自身の権限で管理・執行できない学生などによる代理申請。
②申請者の所属する研究室が、過去ARIM事業による共用設備の利用がある。
B)資本金の額または出資の総額が3億円以下、もしくは従業員数が300名以下の中小企業の研究者。ただし、次のいずれかに該当する企業からは、原則として申請を認めない。
①ARIM事業による共用設備の利用がある。
②発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する。
③発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有する。
④大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める。
なお、大規模な災害など研究活動が著しく阻害される状況が発生した場合には、その地域の研究者に対し支援が検討される場合がある。
利用形態
ARIM事業における利用形態のうち、機器利用、技術補助または技術代行のいずれかで、かつ、共用設備の利用により創出されるデータの提供に同意(*)するものに限る。
(*)支援結果の成否に関わらず、利用した機器より得られたデータはご提供いただきます。ただし、ご提供頂くデータの範囲については支援機関により異なります。
その他条件
1)ARIM事業の業務従事者は申請することはできない。
2)目的が同一である利用課題であっても、複数の支援機関の共用設備を利用する場合は複数件の応募を可能とする。ただし、申請額総額の上限は下記の補助金額とする。
3)旅費につきましては、NIMSの旅費規程に従い支出されます
補助金額
本制度による補助の対象は、支援機関におけるARIM事業に登録した共用設備の利用料金であるが、遠隔地(鉄道による移動距離で100㎞以上を伴うものに限る)からの移動を必要とする場合は旅費も補助の対象とする。また、補助金額は申請1件につき税込み20万円を上限とするが、これは利用料金および旅費の見積もり額の合計であり、このうち、旅費については5万円を上限とする。
注1)補助金額の上限が税込み20万円であって、利用課題の総利用額が20万円を超えたとしても、利用者の自己負担等により賄う場合には問題ない。ただし、申請書の経費内訳には税込み20万円以内となる見積もりを記載すること。
注2)同一の利用者が複数件の課題を申請することは可能だが、補助金額の合計は税込み20万円を上限とする。
注3)旅費の補助については、国立研究開発法人物質・材料研究機構の旅費規程に従って支給する。
申請方法
(1)利用者が利用を希望する共用設備を管理する支援機関と具体的な利用内容を相談し、支援機関が申請条件等に合致すると認める場合、利用者は別紙様式1を用いて、マテリアル先端リサーチインフラセンターハブ試行的利用事務局(arim-trial_use@nims.go.jp)宛に申請書を提出すること。なお、試行的利用課題として承認される前に利用が開始された場合は補助の対象としないので、注意すること。
(2)利用課題の申請時期は随時可能であるが、おおむね令和7年2月末日を提出期限とする。ただし、令和6年度の日付の請求書が発行できることが条件となるため、請求書の発行については支援機関に確認すること。なお、3月の日付の請求書の場合、翌年度の支払いとなる場合がある。
(3)補助の可否は申請順に判断することとしており、本制度に係る予算の総額に達した場合は、上記の提出期限以前でも募集を終了する場合がある。
- R7年度 試行的利用実施要領 [PDF形式/510.39KB]
- 【別紙様式1】 令和7年度 試行的利用課題申請書 [WORD形式/35.02KB]
採択通知
申請のあった利用課題については、横断技術領域責任者および運営機構業務実施者による審査を行う。審査期間はおおむね2週間程度を予定しているが、多数の申請が同一期間にあった場合は、審査期間が延長する場合がある。
採否通知はマテリアル先端リサーチインフラセンターハブ試行的利用事務局より、申請者および支援機関代表者宛に通知する。
利用終了後の手続き
(1)利用者は、速やかに別紙様式2を用いて実施報告書をマテリアル先端リサーチインフラセンターハブ試行的利用事務局(arim-trial_use@nims.go.jp)宛に提出すること。なお、本制度に基づく実施報告書はARIM事業の利用報告書とはみなされないので、注意すること。
(2)支援機関は、利用実績に基づいて算出して請求書を作成し、マテリアル先端リサーチインフラセンターハブ試行的利用事務局(arim-trial_use@nims.go.jp)宛てに請求すること。なお、研究の進展等により利用料金が当初の見積もりと異なる場合には、金額の増減に関わらず、「経費内訳変更理由書」を提出すること。ただし、補助金額は税込み20万円が上限であることは変わらないことから、請求書の作成時に注意すること。センターハブは請求書に基づいて支援機関に支払いを行う。
(3)利用計画によって支払いを複数回に分けて行う必要がある場合には、支援機関はマテリアル先端リサーチインフラセンターハブ試行的利用事務局(arim-trial_use@nims.go.jp)に連絡し、具体的な方法について合意を得ること。
(4)申請伴って提供された個人情報については、本制度を運用するために必要な範囲においてのみ利用される。ただし、採択された利用課題に係る申請者の氏名、所属機関、支援機関担当者氏名、申請課題名等が利用報告書とともに公開されることについては、その他のARIM利用課題と同一である。